「シマアジが全然釣れない…」そんな悩みを抱えていませんか?
この完全マニュアルを読めば、ボウズ(釣果ゼロ)になることはもうありません。実際に多くの釣り人が実践し、確実な釣果を上げている方法を体系的にお伝えします。
第1章:道具選びの完全ガイド
竿選びの黄金ルール
おすすめ竿
竿選びのポイント
- 長さ:3.0〜3.6m
- 調子:7:3調子(穂先が柔らかめ)
- 適合オモリ:15〜40号
海上釣り堀はイケスの上で釣りをして、仕掛けは足元に落とすだけでいいから、竿の長さは3m前後で大丈夫です。施設によって長さ制限がありますが、4m以内なら全国どこでも対応できます。
調子は穂先が柔らかいほうが食い込みがいいし、アタリを取りやすいので初心者にもおすすめです。適合オモリは竿の強度を示す指標でもあるから、大物狙いほど重いオモリに対応したほうがいいです。
仕掛け完全セッティング
基本仕掛け構成
- 道糸:PE1.5号
- リーダー:フロロカーボン3号(1.5m)
- オモリ:10~20号(潮の流れに応じて調整)
- ハリス:フロロカーボン2号(1.5〜2m)
- 針:シマアジ専用針7号
海上釣り堀で使う仕掛けは、ウキを使ったウキ釣りか、オモリのみのミャク釣りになります。
ウキ釣りはウキの大きさにオモリを合わせるので、5~10号程度になります。ミャク釣りは潮の流れに負けないよう、15号前後から複数種類を用意しておくと安心です。
第2章:エサ選びと下処理の完全版
最強エサランキング
- 活きアジ(泳がせ釣り用)
- ボイルオキアミ(塩もみ処理済み)
- 生ミック(アミノ酸配合)
- 練り餌(マルキュー海上釣堀専用)
シマアジ狙いのエサはこれらが定番です。
放流される魚は養殖なので、練り餌や生ミックへの反応がいい傾向があります。オキアミは必ず合うとは限りませんが、他のマダイや根魚も反応するから万能に扱えます。
活きアジは最終手段ともいえるエサで、活きた小魚を使うことでシマアジの闘争本能を呼び起こす方法になります。青物を取り扱っている施設なら販売していることが多いですね。
エサの下処理方法
もし冷凍のエビを使う場合、人間が食べやすいように下処理をしたほうが、魚の食いも良くなる傾向があります。特にアミノ酸添加物に漬けるなど、ひと工夫することで釣果に違いが出ることも。
生エビの処理手順
- 背わたを爪楊枝で除去
- 塩水で軽くもみ洗い
- キッチンペーパーで水分除去
- アミノ酸パウダーをまぶす
必ずここまでやる必要はないですが、エビの殻を剥くか剥かないかでも違いはでます。例えばブラックタイガーを使うなら、殻付きだと黒い色なので、水中の視認性は悪くなります。殻を向けば白身になるから目立ちやすく、背わたを取ることでより白を目立たせることができます。
キッチンペーパーで水分を拭き取るのは、保存を長持ちさせるテクニックです。塩水で軽く洗うのも身を引き締めるためで、針持ちが良くなるメリットがあります。
第3章:棚取りの科学的アプローチ
魚釣りで一番重要なのは「棚取り」です。
海上釣り堀における棚取りは地味に難しい。なにしろ、イケス内の水深は統一規格されているわけじゃないですからね……。落としすぎると網にかかるので、初見でギリギリを攻めるのはリスクが大きすぎます。
シマアジは自分の目線より上のエサに反応するため、釣りの棚はシマアジが泳いでいる水深より少し上に設定する必要があります。棚を自分で見つける楽しみもありますが、海上釣り堀では施設のスタッフにアドバイスをもらったほうが確実です。
時間別棚取り表
- 6:00-9:00:底から1〜2m上
- 9:00-15:00:中層(水深の40〜60%)
- 15:00-18:00:中層〜表層
早朝は低活性の状態か高活性のどちらかなので、まずは低活性を狙うように底から探るのが効率的です。時間とともに棚を上に上げていく感じで、アタリがなければ10cm変えてみるなど、こまめな調整が釣果を伸ばすコツです。
潮流による調整
- 潮が速い:オモリを重く、棚を深めに
- 潮が緩い:オモリを軽く、棚を浅めに
- 二枚潮:中間の棚を重点的に探る
海上釣り堀の施設は湾内にあるので、外洋ほど潮流は起きません。とはいえ、大潮で上げ下げしている時はそれなりに動くので、仕掛けが軽すぎると水中で斜めになりすぎて、イケスの網に引っかかりやすくなってしまいます。
ウキ釣りでオモリを調整するのは困難ですけど、ミャク釣りはオモリを変えやすいメリットがあるので、潮流があっても底付近を丁寧に探る場合に有効です。
第4章:アタリからやり取りまで
シマアジのアタリパターン
- 前アタリ:竿先がピクピク動く
- 本アタリ:竿全体がゆっくり引き込まれる
- 追い食い:一度止まってから再度引き込む
シマアジは口が大型魚ほど大きくないため、エサをついばむようなアタリが多いです。
ミャク釣りは口に入れた瞬間にアタリがわかりますが、そこではアワセずに、相手から引っ張られた時にアワセるのが確実に釣り上げるコツです。しかし低活性だとわかりきっている時は、コツンと小さなアタリでも即アワセするほうが有効です。
時と場合によって対応は変わるので、アタリからのアワセは臨機応変に考えましょう。
やり取りの極意
- アワセは軽く、確実に
- 無理な巻き上げは禁物
- 口が切れやすいため慎重に
シマアジの口は柔らかく、針が抜けにくいカンヌキ(口の付け根部分)にかかっても、引っ張りすぎると口が切れてバレてしまうことがあります。これを回避するのはファイトのテクニック次第。
コツとしては、ドラグを緩めにして魚への負荷をかけすぎないこと。竿の弾力をいかして反発で引っ張るようにすることで、口部分への負担が少なくなるので、口切れでバレることは少なくなります。
難しい問題は、青物の取り込みには時間制限がある施設が多いことです。
制限以内に釣り上げるため無理しようとすると、ドラグを締めてパワーで対応するわけですが、これだとシマアジはバレやすくなってしまいます。口切れをギリギリで回避する塩梅の設定は、体験と経験で覚えるしかないので、正解は魚のサイズやその場その時で変わります。
第5章:状況別対応策
活性が低い時の対策
- 仕掛けをより細く
- エサを小さくカット
- 棚をこまめに変更
シマアジの姿は見えても釣れない時は、活性が低く警戒心が強くなっていると考えましょう。
そんな時は投げやりにエサを入れるのではなく、10分くらい竿を上げて休憩をするなど、魚に同じエサを見続けさせない工夫も大切です。エサを少ししか食べてないなら、針先に小さく付けて針を小さくするとか、仕掛けのハリスを細くするなどの対処方法があります。
他の魚が邪魔する時
- ハリスを長めに設定
- 針を小さくしてシマアジ専用に
- エサを硬めのものに変更
水温が高めの時期は、目的のシマアジ以外が積極的に絡んでくることもあります。目標以外はエサ取りとして認識するのであれば、よりシマアジだけを狙うようなセッティングにしましょう。
もっとも効果的なのは、活きたアジを使う泳がせ釣りに変更すること。活きエサならシマアジやブリにヒラマサなどの青物が積極的に来るので、狙い撃ちすることができます。
【まとめ】ボウズ回避率100%に近づけるのは努力次第
この完全マニュアル通りに実践すれば、シマアジのボウズ回避率は100%に近づきます。
どんな魚でも共通するのは、まず魚の習性を理解すること。次に適切な棚取りとエサ選択。そして釣れやすい時間帯を狙う「時合」に集中して取り組むことが大切です。
いくら管理されている海上釣り堀でも、自然の海で行う釣りですから、毎回同じ施設に通っていたとしても、全開と同じ環境になるとは限りません。その場その時で臨機応変に対応する知識と技術があってこそ、ボウズ回避は100%に近づいていきます。
それでも最低条件として、そこに魚が居ることが最も重要です。施設の放流タイミングは把握しておき、そのタイミングで集中して攻略することが大切です。
さらに上級テクニックを学びたい方は、次の記事もご覧ください。

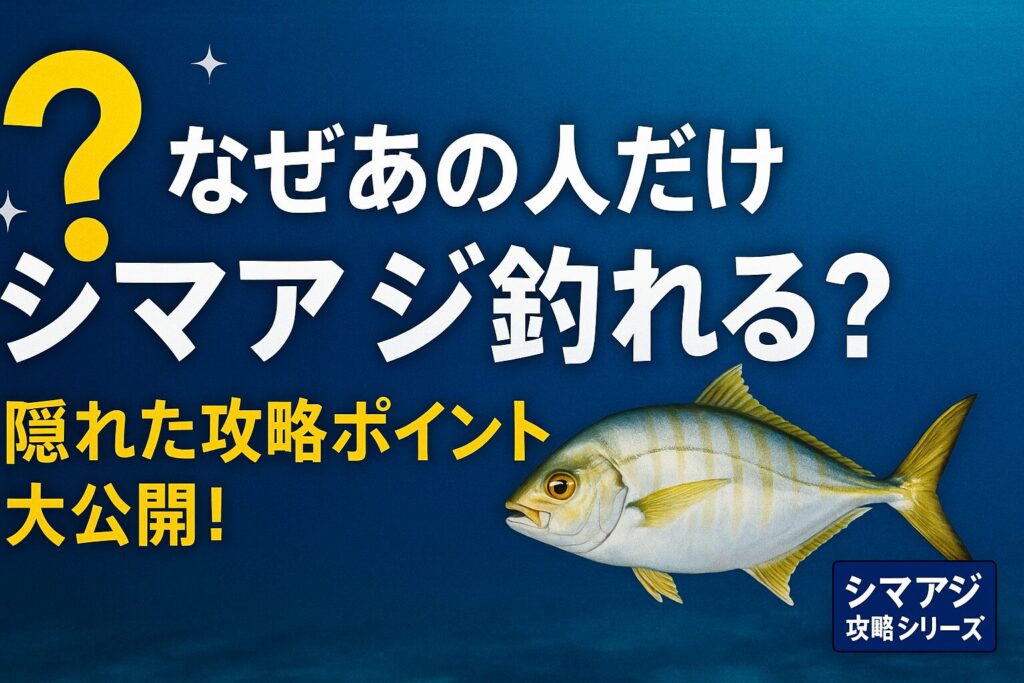
コメント